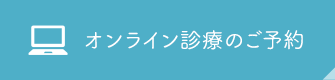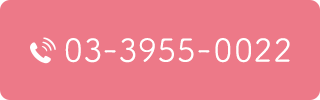過活動膀胱とは
 過活動膀胱は、尿意切迫感(突然、我慢できないほど強い尿意が現れること)が発生し、頻尿(トイレの回数が増えること)や夜間頻尿(就寝時に何回もトイレで起きること)を伴う疾患です。
過活動膀胱は、尿意切迫感(突然、我慢できないほど強い尿意が現れること)が発生し、頻尿(トイレの回数が増えること)や夜間頻尿(就寝時に何回もトイレで起きること)を伴う疾患です。
また、場合によっては、急に強い尿意が起き、尿漏れが生じる「切迫性尿失禁」も伴います。過活動膀胱は、「尿意切迫感」の有無で診断を下します。
過活動膀胱の頻度
日本では40歳以上の男女の14.1%が、過活動膀胱を発症していると報告されています。また、そのうちの約半数が尿失禁(切迫性尿失禁)を伴っていると言われています。
原因
 過活動膀胱の原因は、脳血管障害やパーキンソン病、認知症、多発性硬化症、脊髄腫瘍、頸椎症、脊柱管狭窄症などの神経に原因があるものと、「前立腺肥大症」や「加齢」などが原因で発症する非神経因性があります。
過活動膀胱の原因は、脳血管障害やパーキンソン病、認知症、多発性硬化症、脊髄腫瘍、頸椎症、脊柱管狭窄症などの神経に原因があるものと、「前立腺肥大症」や「加齢」などが原因で発症する非神経因性があります。
検査・診断
 尿意切迫感の症状がありましたら過活動膀胱と診断されます。頻尿や切迫性尿失禁などを伴っている場合、過活動膀胱の可能性はさらに高まります。過活動膀胱の診断や重症度は、「過活動膀胱症状質問票(OABSS)」を使って採点します。この質問票は、患者様による自己採点で記入するテストになっています。
尿意切迫感の症状がありましたら過活動膀胱と診断されます。頻尿や切迫性尿失禁などを伴っている場合、過活動膀胱の可能性はさらに高まります。過活動膀胱の診断や重症度は、「過活動膀胱症状質問票(OABSS)」を使って採点します。この質問票は、患者様による自己採点で記入するテストになっています。
必要に応じて尿検査や超音波検査などの検査を行い、他疾患の可能性がないと判断しましたら、過活動膀胱と確定診断します。
治療法
行動療法
行動療法は副作用のリスクがないため、安心して他治療との併用ができます。
生活指導
過剰な水分摂取をやめたり、カフェインの摂取量をおさえたりします。また、「早めにトイレに行く」「外出先のトイレの有無を確認しておく」、などの行動を習慣化させ、切迫性尿失禁を予防します。
高齢者の方には、トイレ環境の整備や着衣の工夫など、日常生活における工夫なども指導します。
膀胱訓練
膀胱訓練とは、少しずつ排尿する間隔を長くすることで、膀胱容量を増加させる訓練法のことです。まずは排尿計画を作成し、短時間から始めて少しずつ排尿間隔を伸ばしていきます。最終的には、2~3時間の排尿間隔を空けることをゴールにします。
骨盤底筋訓練(体操)
腹筋に力が入らないように、膣や肛門を締める訓練法です。特に女性に指導する訓練法で、腹圧性尿失禁に対して広く実施されています。過活動膀胱の改善にも効果的です。
薬物療法
抗コリン薬
膀胱の収縮を抑制させ、尿意切迫感も一緒に改善する薬剤です。口の渇きや便秘といった副作用がしばしば見られます。
※閉塞隅角緑内症の方に処方することはできません
β3受容体作動薬
膀胱が尿を溜めた時の、拡張を促進させる薬剤です。尿意切迫感の改善効果もあります。口の渇きや便秘といった副作用が起きる傾向も少ないと言われています。現在、保険承認されている薬剤では、ベタニスがあります。
フラボキサートや漢方薬、その他薬剤
上記の治療薬の服用が難しい時に処方します。